10月21日付の読売新聞に、李在明研究と言う連載の「中」が載っていました。
そこで、李在明氏がどういう評価をされているのか、という話として、韓国での夕刊紙、文化日報が行った大統領候補の資質を評価する世論調査の結果が持ち出されていて、与野党有力候補4人の中で、「道徳性」が最下位だけれども、「推進力」と「国民との意思疎通能力」がトップであるということが言われていました。
ちなみにスコアとしては、推進力(5点満点中3.8)の方が、意思疎通能力(5点満点中3.2)よりもだいぶ大きいです。あと、公正な国政運営も低めに出ています。
この「公正な国政運営」「道徳性」よりも「推進力」「国民との意思疎通能力」というのは、まさに「改革派」の評価ですよね。国民との意思疎通能力よりも推進力の方が評価されていると言う点も含めて。
で、こういう「改革派」がどこでも求められているんだろうなぁ、と言うのが現在の私の認識です。
なぜそうなるかという推測としては、やはりインターネットによって視野が広がったように思えるようになったことが大きいのでは?と言いますか。
新聞、テレビのように事前に誰かによって選別された意見と、自分の人脈で回ってきた話でいろんなことを評価する時代は、現在でいう「なんでマスコミは〇〇を取り上げないんだ」というような不満も、そこを知る可能性が今より低かったせいで今よりは少なかっただろうと言いますか。
下手をすると「マスコミも人脈の中で動いてるから限界あるよね」程度の期待の人が多くて、そこまで高い期待は寄せられていなかった可能性もあると思います。
一方で現代は「困っている」「こういう問題がある」と言うことが人脈を超えて知られる可能性がどんどん増えていて、他人に認知している問題の量がとても増えていて。
さらにその問題に対して「解決すべき」と自分と同じことを思っている人も自分の人脈よりも幅広く見つかる。
そうなると「どうして問題が解決されないんだ」という思いはどんどん募っていくわけで、解決を願う思い・期待は古よりも大きくなるのではないかと思います。
一方、道徳性に関しては、「問題がいっぱい見つかる」状態では逆に、「道徳性にケチをつけやすい状態なんだ」とも言えたり、「問題で得をする人間が問題を解決しようとしている私を貶めようとしている」なんて言ったりする、言い訳ができやすくなっていたりするでしょうし、よその人の道徳性よりも自分が重要だと思う問題の解決を優先すると言うのは当然の優先順位ではあるように思います。
私が「問題解決を優先する」系の言説に条件反射として警戒してしまうのは、こういう「何らかの問題解決を優先することにより、他の問題を放置・悪化させる」ことへの警戒心が大きいのだろうと思います。
「対決よりも解決」とか「改革を止めるな」とか「できない理由を考えるのはやめました」とか、僕にとっては同じ枠組みです。
なぜできないのか、考えたらきりがないと言うのは、私は問題の温存だと思っているので。
しかし、一方でこの警戒心が強すぎると「問題を温存する」「問題を放置する」ことになってしまって、解決できるタイミングを逃してしまったりするというのも確かにそうではあるのですよね。
こういう現状の環境が「推進力」についての優先順位がすごく高まっている要因になっていると言いますか、「変えられると言う希望」「変えてほしいと言う希望」にあふれていて、それを満たす推進力のある政治家を求めていると言うのが、現在のいろんなところでの有権者の要望なのかな、と改めて思いました。
(アメリカの「change」や「MAGA」、イギリスのブレグジット、フィリピンのドゥテルテやブラジルのボルソナロの先鋭的な反汚職姿勢とかもそうなのでしょう。)


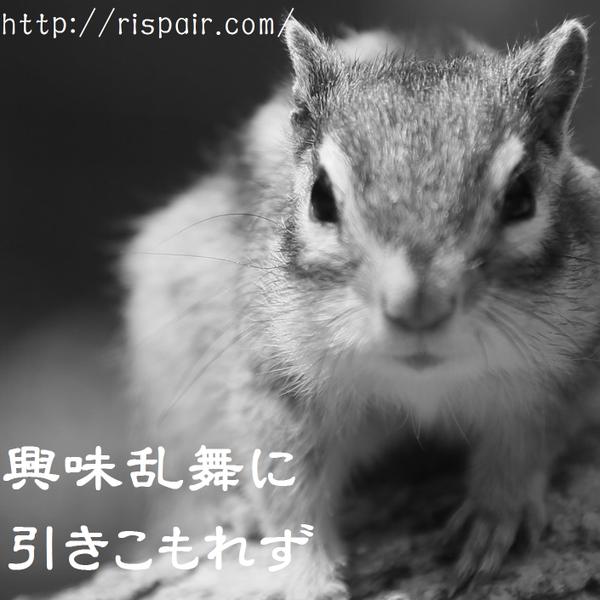
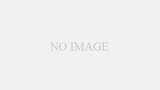
コメント