「海外では引きこもりやオタクが外に出てポケモンをするようになった」
「精神科医より漫画の方がよほど効果が出る」
【ポケモンGO】「引きこもりが外に出る」と麻生太郎財務相、ポケモンGOを語る – 産経ニュース
麻生副総理がポケモンGOについて、記者の質問に答えた内容が非常に危ないもののように思えたので、いくつか問題点を書き出しておこうと思います。
オタク偏見問題
麻生氏がさり気なく「オタク」を外に出ない存在として扱っています。実際にはオタクにも様々な方が居て、積極的に外出するオタクも多いからこそ、経済的にも注目されるのだろうと思うわけです。
しかし、その一方で麻生氏が言うような『外出しない』みたいな根暗な存在として「オタク」が描かれてしまう、という偏見に対して反発している人も多いのではないでしょうか?
産経新聞いわく『オタクからの支持が高い』麻生氏ですが、今回はオタクの偏見を撒き散らす役割を担ってしまっているように感じます。これでも支持は続くのでしょうか?
財務大臣が精神科医批判にも受け取れる言及
麻生氏は財務大臣です。財務大臣は、予算形成で巨大権限を持つと言われる財務省のトップです。
予算で毎年問題としてあげつらわれるのは社会保障関連費用の増大です。
財務省は、社会保障の「重点化・効率化」「国民負担の拡大を防ぐ」という名目の下に、社会保障関連費用で削減できそうな対象をずっと探しています。
そういう背景を考慮すると「精神科医より漫画の方が効果が出る」という発言を財務大臣が行うというのは、関連費用の削減の名目に利用されるのではないか?という憶測を私はしてしまいます。
こういうセンシティブな部分に触れてしまうような発言を財務大臣は行うべきではないと思うんですが、麻生氏がそんな考慮ができるなら、これまで起こしてきた舌禍の殆どが起こっていなかったでしょうね。
ひきこもり治療への認識が怪しい
ひきこもりが外に出るというのは、確かな一歩ではあると思います。そして人によっては、精神科医の促しよりも、ゲームのほうが外出する動機付けの効果が強い場合があると思います。そういう点でゲームが注目されても不思議ではないと思いますし、実際に精神科医の斎藤環氏はTwitterにてポケモンGOのベースになっているIngressを患者さんにおすすめしていたと述べています。
その一方で、そもそも「ひきこもり」というものは、単に『部屋から出れば解決』というものではない、というように、例えば政府も過去に言及している斎藤環氏が初出の「社会的ひきこもり」という用語に関連する言説や、「準ひきこもり」という言説などを読んで、私は思いました。
さらに、精神科医の斎藤環氏の言及を見て私は確信したのですが、ゲームはあくまで問題の一部分を解決するために利用できる「画期的な?ツール」でしかないと思うんです。
精神科医は、そういうゲームを含めたツールを適切に活用できるように全体的に調整・デザインしていくことが役割であると思うんです。
つまり、精神科医とゲームは麻生氏が述べたように「精神科医よりゲームのほうが効果がある」というような比較するような関係ではなくて、うまく共存していくような関係性にあると思うんです。
それに対して「〇〇より〇〇」という言及をしてしまうのは、間違った認識を拡散することになりかねないように私は思います。
まとめ
ポケモンGOの話をしていたのに、何故かゲームではなく『精神科医より漫画のほうが』と言い出していることから察するに、大雑把に『マンガすごい』と言っておけば話題になり支持が集まると思って、エピソードを秘書か誰かから教わって言及したのかもしれませんが、その大雑把な言及に複数の問題点が含まれているのが麻生氏らしいと思いました。
個人的に麻生氏に何言ってもしょうがないと思うので、根本的な問題について、少しでも問題が解決に近づくように、これからも問題に気を向けて生活していけたら良いな、と思いました。
以下、参考
ともあれ私は、著書の中で「社会的ひきこもり」を下記のように定義づけた。
・20代後半までに問題化
・6カ月以上、自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続
・ほかの精神障害がその第一の原因とは考えにくい
ひきこもり 斎藤環 治療 デイケア
厚生労働省の定義などを参考にすると、自宅にひきこもって学校や仕事に行かずに、家族以外との親密な対人関係がない状態が6ヵ月以上続いている状態を指します。「社会的ひきこもり」であるかどうかという定義や基準にあまりこだわらず、本人や家族が何らかの困難を感じられているのであれば、支援が必要な状態であると考えてください。
〈社会的ひきこもり〉社会的ひきこもりQ&A(心の健康について)[京都府精神保健福祉総合センター]
実態は上述したように、発達障がい・精神障がい・性格のいずれかだから、そのいずれかを明確にしない曖昧な「社会的ひきこもり」支援(多くは古くからある当事者同士の交流の補助的支援)は、問題の明確化を遅延させる。そうして当事者は年齢を重ねていく。
「社会的ひきこもり」はいらない(田中俊英) – 個人 – Yahoo!ニュース
推計70万人の「引きこもり」群は、統合失調症などの病気ではなく、家事や育児をしているわけでもなく、6か月以上にわたって「趣味の用事のときだけ外出する」「近所のコンビニなどには出かける」「自室からは出るが、家からは出られない」「自室からはほとんど出ない」状態のいずれかの人たちと定義づけている。
なかでも、「趣味のときだけ外出する」状態の人たちが推計46万人に上り、日本の「引きこもり」の中枢を占めたことに、高塚教授は「準引きこもり」群として注目する。
「趣味なら出かけられる人たちも、基本的に、働いていないし、勉強もしていない。家族以外との交流も避けていて、6ヵ月以上経っているとなれば、少し健康度の高い引きこもりなのではないか」
そう高塚教授は説明する。
「どこかで生の実感を欲しがっている。それが行きつくところは、旅行や自分の趣味などであって、辛うじてそういう趣味的なものを見出しているのです」
“予備軍”155万人の衝撃!「趣味のときだけ外出する」新たな引きこもりが急増中|男の健康|ダイヤモンド・オンライン
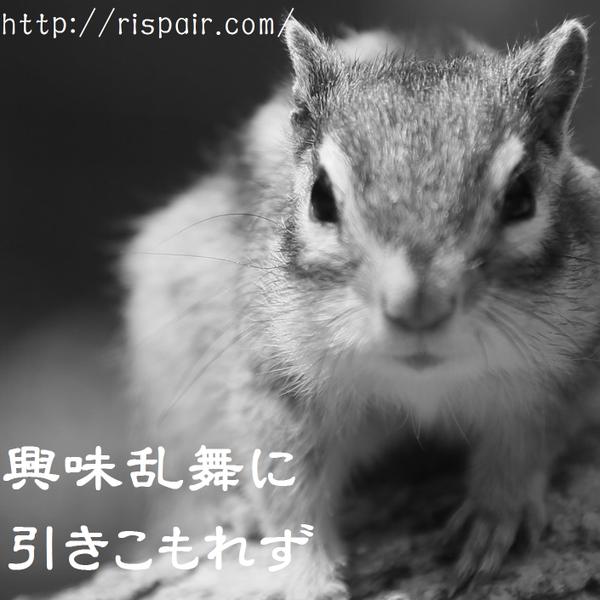
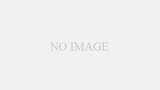
コメント