先日、引用した部分の後に『主張はキャッチーだが、あまりしっかりした根拠はない。(中略)だからこれは、結局は右派ウケするプロパガンダなのである。』と書いてある文書の、『プロパガンダ』の中身を紹介する部分を抜き出して真実であるかのように拡散する佐々木俊尚氏とリプライ群についてブログに書きました。
これを書いたあと、また新たにそういう拡散の仕方をしている人がTwitterで流れてきました。(あと唐沢俊一が見事に乗っかってるのも見つけました)
前に書いたブログと同じような話をしますが、明らかに筆者は『右派からの左派に対するカウンターとして、ようやくまともな指摘が出てきたね… って感じで着地してる。』なんて着地のさせ方はしていません。
多分、まともな指摘云々というのは、元の文章の『とはいえ個人的に思うのは、ようやく米国の右派が、左派と勝負できるだけのナラティヴを手に入れつつあるのだな、ということだ。』という部分とかを読んで導き出したのではないかと思います。『左派と勝負できるだけのナラティヴ』というのを、左派と勝負できるまともな指摘が出来た、と言っているとでも思ったのでしょう。多分。(転載した?ニューズウィークも冒頭に左派と勝負できるナラティヴ…の部分を持ってきてますし。)
とはいえ個人的に思うのは、ようやく米国の右派が、左派と勝負できるだけのナラティヴを手に入れつつあるのだな、ということだ。レーガン以降の右派は、右派の外へリーチし、アピールするような言説をうまく構築できなかった。今さら神を崇めよと言ったところで時代錯誤のそしりは免れないし、小さな政府、反共、自由競争といったお題目の輝きも冷戦後はだんだん色褪せた。いわゆるMAGAもドナルド・トランプという個人のカリスマに多くを負っていて、そう長続きするとは思えない。おそらく「贅沢な信念」のような焼き直しの社会保守主義が、今後そのニッチを埋めるのだろう。
アメリカで話題、意識高い系へのカウンター「贅沢品としての信念」(luxury beliefs)とは|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
ここで重要なのは、この文章における『左派と勝負できるだけのナラティヴ』の部分は、「正しいから勝負できている」という意味で書いていることではないということです。
「ナラティヴ」というのは、「物語」や「語り」「言説」みたいな意味の言葉であり、ここでは「右派も、左派みたいに外にアピールできる、外で話題になる、外の人が乗れる言説を手に入れたんだね」的な話をしているのだと思われます。
ナラティブという言葉は、元々はフランス語が語源であり、直訳すると「物語」「言説」「語り」という意味です。ナラティブは、物語の力を活用することで、製品やサービスの魅力を伝える手法です。物語は人々の心に響き、共感を生み出す力があります。また、「語り」という意味からも分かるように、ナラティブは情報を伝える手段としても利用されます。
ナラティブとは何か?意味やビジネスで活用する手法をわかりやすく紹介 | 株式会社ソフィア
『物語は人々の心に響き、共感を生み出す力があります。』
一方で、この共感を生むとか、アピールできる、とかは、正しいからそうできる、とは限りません。客観的には正しくなかろうが主観的な共感は生まれます。
では、今回右派が生み出した、外にアピールできるナラティブは、本当に『まともな指摘』だったのか。
この右派のナラティヴのまともさについては、こう文章内に書かれています。
一応指摘しておくと、ヘンダーソンの主張はキャッチーだが、あまりしっかりした根拠はない。そもそも、考え無しに流行りの思想に飛びつくのは別に上流階級に限らないし、ピーター・ティールのように右派の金持ちはいくらでもいる(むしろ最近では多数派かもしれない)。だから、プログレッシブなことを言わなければ絶対にステータスが上がらないというわけではない。
また、そもそもリベラルっぽいことを口にするから必ず社会的評価が上がるというものでもない。具体的にこう警察を改革するというのなら分かるが、大真面目に警察を廃止しろという金持ちがいれば、仲間内にもただバカにされるだけだろう。薬物に限らず、自由を享受するには(自制心も含めた)能力がいる、というのは確かだが、だからといって自由のほうを狭めるというのも妙な話だ。だからこれは、結局は右派ウケするプロパガンダなのである。
アメリカで話題、意識高い系へのカウンター「贅沢品としての信念」(luxury beliefs)とは|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
『一応指摘しておくと、ヘンダーソンの主張はキャッチーだが、あまりしっかりした根拠はない。』から始まり、諸々反論し『だからこれは、結局は右派ウケするプロパガンダなのである。』という締めで終わる段落が存在するのです。
この筆者が『一応指摘して』おいた部分が、ナラティヴを正しいと思った様々な人たちから見事に無視されているわけです。
「考え無しに流行りの思想に飛びつくのは別に上流階級に限らない」「右派の金持ちはいくらでもいる(むしろ最近では多数派かもしれない)」「リベラルっぽいことを口にするから必ず社会的評価が上がるというものでもない」「自由を享受するには(自制心も含めた)能力がいる、というのは確かだが、だからといって自由のほうを狭めるというのも妙な話」
この辺の筆者の指摘が、誰かの手で指摘に反論されているわけでもなく、丸々無視され、筆者は右派のナラティヴをまともな指摘と思っているとすら勘違いされて、ナラティヴ紹介部分だけ一人歩きしているのだ。筆者は右派のプロパガンダとすら書いているのに。
さらに強烈なのは、記事の締めとして、今回の(右派のナラティヴの)ような主張をしていた人を過去に知っている、とチリで独裁政権を敷いたピノチェトを持ってきて『この種の議論は、結局 エリートの 自己正当化に使われる』と述べていることです。
個人的には別に上流階級というわけでもないのだが、この種の考えにはいまいち乗れない。というのも、私は「贅沢な信念」と似たようなことを言っていた人物を一人知っているからだ。思うにこの種の議論は、結局 エリートの 自己正当化に使われるのである。
アメリカで話題、意識高い系へのカウンター「贅沢品としての信念」(luxury beliefs)とは|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト1974年、ルター派教会のヘルムート・フレンツ監督と、カトリックのエンリケ・アルベアール司教がピノチェトに面会し、「肉体的圧力(ピノチェトを憚って「拷問」の用語を避けた)」を止めるよう申し入れた。ピノチェトは自ら「拷問のことかね?」と返し、「あんた方(聖職者)は、哀れみ深く情け深いという贅沢を自分に許すことができる。しかし、私は軍人だ。国家元首として、チリ国民全体に責任を負っている。共産主義の疫病が国民の中に入り込んだのだ。だから、私は共産主義を根絶しなければならない。(中略)彼らは拷問にかけられなければならない。そうしない限り、彼らは自白しない。解ってもらえるかな。拷問は共産主義を根絶するために必要なのだ。祖国の幸福のために必要なのだ。」(アウグスト・ピノチェト)
今回の贅沢な信念を金持ちが言うことで貧乏人が苦しむ…ということと同じことを言っている、としてピノチェトが、「拷問は祖国の幸福のために共産主義を根絶するのに必要なのに、拷問をやめろというのは聖職者の贅沢だ」と主張している話を持ってきているのです。
結局、上流階級は云々、という批判が、回り回ってエリートによる拷問などの強引な社会統治の自己正当化に使われる。
これほど明確な批判はないと思います。(このブログの冒頭に貼った「安全地帯から自分はコスト負担が低い理想論を言うには良くないね」というツイートは、見事にピノチェトと同じ文脈に乗るのではないだろうか。)
しかし、右派のナラティヴを正しいと思った人たちはこの部分にも反応しないようです。(むしろピノチェトをナラティブの正しさの根拠として読んでしまいそうだ)
前回の記事で知ったきっかけとして紹介したツイートに対するリプライのやり取りとして、飛びつき具合を見ると…みたいな話をしていたが、この記事に対して筆者の批判を無視してナラティヴ紹介部分を真に受けて拡散する人達を見ると、本当にこのプロパガンダは一部の人達に強力に効くのだな、と実感できます。
私自身は右派のナラティヴは嫌いな一方、左派のナラティヴに親和性のある人間なので、そういうナラティヴに囚われすぎないように気をつけようと自戒する話でもあるのですが。
一方で、その後の否定的な見解込みで紹介したであろう部分が、その紹介した部分を肯定するために引用されて流されていく事態を見ると、一ブログ書きとしては「そういうの本当に困る…」としか言いようがないです。
いくら一度世に放った文章がどう流通するかは書いた人にコントロールできないことだとしてもさぁ…。
以下 2024/06/07 午前6時57分 追記
触れようとして忘れていましたが、今回の贅沢な信念、みたいな話って、最近特に既視感のある話だよな…と以下のツイートを見て思いました。

「バラモン左翼」という言葉はかなり流行したが、右翼のリベラル批判の文脈でしか理解しない人も多く、造語主ピケティの真意と乖離している感もあった。
【書方箋 この本、効キマス】第32回 『資本とイデオロギー』 トマ・ピケティ著/濱口 桂一郎|書評|労働新聞社
あと、チリ・クーデターのことを調べていたとき、Amazonで検索したら『アメリカはクーデターによって、社会主義国家になってしまった 』なんていう、ディープステイトがどうこう言ってる本が検索に引っかかってしまったのだが、本の概要に『私の出身地であるイリノイ州では以前から民主党所属の候補しか知事や市長になることができないのだ。』と堂々とデタラメが書いていて笑ってしまった。(2021年時点で、直近の選挙でイリノイ州知事選もシカゴ市長選も、民主党系が勝ったという意味のことを、仰々しく陰謀めいて言ったなら印象操作も甚だしい)
たしかにシカゴ市は民主党系が鉄板らしいが、イリノイ州知事は2015年から19年まで、共和党系の知事だったはずだ。(リベラルな共和党系ではあった&民主党系主導の議会との対立で色々あったらしいが。)

また、シカゴに次ぐイリノイ州第二の都市であるAuroraの市長はリベラル系ではあるが、2022年に共和党員として州知事選予備選に出た人であり、決して民主党所属ではない。

このようなレベルの話すら間違っている本の著者を参考にしないほうがいいと思うのですが…
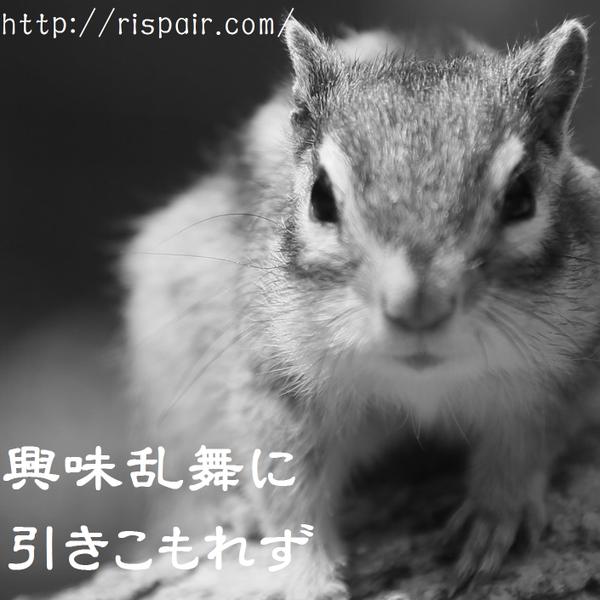
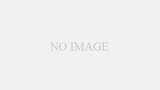
コメント