Twitterで以下の記事が話題になっていました。
TPPの危機は過ぎたと言っていいが。新たな危機は迫っている。
2020年の東京オリンピックである。規制をしたい人々はこれをチャンスと、
日本の色んな文化を「浄化」しようとする作戦を仕掛けてくるだろう。
TPPの時よりも遥かに厳しい戦い。敵は多く、理解を得ずらく、
世論の目は厳しいだろう。
この来るべき次の危機の時、やまだ太郎という人に、
国会議員という身分で居て欲しい。しかし。
やまだ太郎議員はもうすぐ。2016年7月に任期満了により、失職する。
コミケを守る大活躍をした、やまだ太郎議員。
実は2010年の選挙には落選しているのである。
落選したが、2012年に上位当選者が衆議院に鞍替え立候補したために
繰上げ当選したのである。ギリギリの奇跡の巡り合わせが、コミケの危機に、
やまだ太郎さんを議員という立場にしてくれたのである。
果たして、次の選挙は・・・。正直、すげー心配。
今年、2016年夏。7月の参院選。全国どこからでも。やまだ太郎と投票できます。
全国比例区で出馬されると思われるので、全国どこからでも一票入れられる。
所属政党の「日本を元気にする会」でもいいけど、
個人名のほうがよりメッセージが強いかな。
ここで当選すれば、やまだ太郎さんに新たな議員生活6年を与えられる。
俺は動くのが遅すぎたかもしれない。冬のコミケ前にもっと運動して、
冬コミケで皆さんがこの話題を話し合えるようにできていたら、と。
もう参院選は、夏のコミケより先にくるのだ。
遅いことを嘆いてもしかたない。今からでも出来ることをするしか無い。
口コミで広めて欲しい。やまだ太郎議員というコミケを守った勇者が、
今はジャンプで言えば掲載順番が後ろのほう、
磯部磯兵衛の手前、打ち切り寸前の状態なんだよ、と。
んー、ちょっと例えが違うかなあ
むしろもう打ち切りは決定して、時期も決まってるワケか。
一期がもうすぐ終わる「山田太郎(議員の)ものがたり」の二期のために応援を! と。
応援するのに円盤買うのに比べれば、投票するだけとか簡単でしょ。
この記事にあるように山田太郎議員の議員生活が打ち切りの危機に陥っています。
この記事では、その危機についてどのような状況なのか?どういう状況になったらこの打ち切りの危機を乗り越えて次の6年間をゲットできるのか?ということを書いてみようと思います。
所属政党・日本を元気にする会の状況
現在、山田太郎議員は日本を元気にする会の政調会長と幹事長代理という職についています。
この日本を元気にする会は現在、ボロボロとしか言いようが無い状況になっています。
1,政党要件の喪失
まず、日本を元気にする会は国会議員5名で結党された政党でした。
政党には、政党要件というものがあります。政党要件とは政党助成法上に存在する要件の事を指すことが多く、この洋意見を満たすことで、様々なメリットを政党として受けることが出来ます。
一方で、この要件を満たさないと、政党はそこら辺の政治団体として扱われ、様々なメリットを受ける事ができない、政党と比べて大きなハンディを負うことになります。
先ほど『政党“でした”』と書きました。ここで過去形を使ったことには理由があります。
日本を元気にする会は、現在、政党助成法上の政党ではありません。井上義行議員が、自民党会派に入るために離党届を提出、それを受理したために、現在国会議員4名となってしまいました。
政党要件として設定されている要件には以下の二つがあり、この内の一つを満たすことで政党助成法上の政党という存在になることが出来ます。
- 所属国会議員が5名以上であること
- 所属国会議員が1名以上存在し、かつ、前回の衆院選、もしくは前回、前々回の参院選にて、全国を通じた得票率が2%以上であること。
日本を元気にする会は選挙を経た政党ではないため、ふたつ目の要件は満たしようがありません。なのでひとつ目の『国会議員が5名以上』という要件が、満たすことの出来る政党要件となります。
つまり国会議員5名で結党された日本を元気にする会は、1名でも欠けてしまった場合は、その時点で政党助成法上の政党では無くなってしまうのです。
そして現に井上義行議員が欠けたために、日本を元気にする会は政党助成法上の政党では無くなってしまいました。
(また、この政党ではなく政治団体になったこと。その後、参院維新の党と統一会派を結成したことなどにより、ブログをよく見るおときた駿都議会議員と伊藤陽平新宿区議会議員が離党しています。このような政党の根っこを支えるような地方議員さんが抜けてしまったのも日本を元気にする会としては非常に痛いのではないかと思います)
2,政党要件喪失の結果、負うことになったハンディ
日本を元気にする会は政党要件を失いました。その結果負うことになったハンディはいくつもあります。ここでは、その中でも私が認識している、次の参院選に影響するであろうものを幾つかピックアップします。
2-1,政党交付金が無い
先程から『政党助成法』という法律の名前を何度も使っています。この法律は政党交付金を配る対象を選定するための法律です。なので政党交付金はもちろん政党要件喪失した場合、得られません。
日本を元気にする会は昨年一年で、約1億2千万円程の政党交付金が交付されていました。
それが選挙イヤーである今年になって得られないというのは選挙資金を捻出するにあたって大きなハンディとなるのではないでしょうか?
2-2,参院選で全国比例区に名簿を提出する際に、条件が出来る
冒頭に引用したブログ記事に書いてある通り、山田太郎議員は参議院全国比例区選出の国会議員です。
参議院全国比例区の比例名簿は、先程の政党要件を満たしている場合、何も問題なく名簿を提出することが可能です。しかし満たさない場合、別な条件を満たさないと全国比例区にそもそも政治団体として参戦することが出来ないという事になってしまいます。
(細かく言うとここで使う政党要件は公職選挙法の政党要件であって、政党助成法の要件にある前々回の参院選の結果は含まれないものとなっている。このズレに引っかかるのが新党改革という政党で、新党改革は政党助成法的には前々回の参院選で政党要件を満たしているものの、公職選挙法的には政党要件を満たしていない、というズレが生じている 新党改革、公選法上の政党要件満たさず 重複立候補も禁止 :日本経済新聞)
その参院選で政治団体として全国比例区に参戦する条件とは『その届け出によって増加する比例代表候補を含めて、10人以上の候補を擁立すること。』というものです。
そもそも候補者を10名以上だせないような政治団体が、全国比例区だけに出てきて売名しようだなんて10年早い!ということなのでしょう。
ちなみに候補者を立てるには、少なくとも供託金が必要となり、額は都道府県単位の選挙区が一人300万円、全国比例区が一人600万円となっています。
この10候補者分の供託金を用意した上で選挙資金も捻出するというのは、政党交付金がない政治団体には中々厳しいハンディではないかなぁ、と個人的には思います。
ちなみに、参院選の場合、この比例区に出馬できる要件を満たさない場合、公職選挙法上で確認書というものが交付される『確認団体(法律内にはこの名称は出てこない、いわゆる通称)』というものになれず、選挙活動が大きく制限されてしまうというハンディも政治団体は負っているのです。
2-3,いろいろな場面での露出量が減る
国会内では会派という政党とは別の枠組みで活動できるので、どうとでも出来る(現に維新の党と統一会派を組むことで露出量を上げている)のですが、テレビ出演などではそうはいかず、特にNHKの日曜討論などは政党要件を満たしていた時代にもよくわからない規準を満たすことが出来ず、まだ結党もしていなかったおおさか維新の会がよばれた一方で日本を元気にする会や生活の党と山本太郎となかまたちは呼ばれないという事もあった。(日曜討論に呼ばれなかった… 元気と生活、NHKを批判)
このようなテレビ討論への露出もさらに減るでしょうし、選挙時の日本記者クラブが主催する党首討論会も政党要件が規準となる可能性が高く、そこにも出ることが出来ないなど、露出量は明確に減少するだろうと思われます。
山田太郎議員が再選するために必要な数字は?
ここまで日本を元気にする会の状況やハンディを見てきました。
ここではそのハンディを跳ね飛ばし、参院選の全国比例区に出馬できたという前提のもと、山田太郎議員が再選するかどうかを考えるためのデータをいくつか提示したいと思います。
1,前回の参院選の比例区を検証
まず、2013年に行われた参院選での全国比例区の結果を以下に載せます。(以下の政党得票数とは“政党名得票+個人得票”を合計してある数字です。約としているのは千の単位の数字を四捨五入して掲載しているからです。これが政党ごとに議席を割り振る際に参考にされる数字となります データ参考元:朝日新聞デジタル:比例区 – 開票速報 – 2013参院選)
- 自民党 政党得票数 約1846万票 18議席
- 公明党 政党得票数 約757万票 7議席
- 民主党 政党得票数 約713万票 7議席
- 日本維新の会 政党得票数 約636万票 6議席
- 共産党 政党得票数 約515万票 5議席
- みんなの党 政党得票数 約476万票 4議席
- 社民党 政党得票数 約126万票 1議席
- 生活の党 政党得票数 約94万票 0議席
- 新党大地 政党得票数 約52万票 0議席
- 緑の党 政党得票数 約45万票 0議席
- みどりの風 政党得票数 約43万票 0議席
- 幸福実現党 政党得票数 約19万票 0議席
この得票数と議席数をざっと見ていくと、大体100万票弱強で1議席が確保できるのではないか、と推測ができるのではないでしょうか?
ちなみに2010年の参院選では、新党改革が約117万票で1議席確保、2007年参院選では、国民新党が約127万票で1議席確保していることからも、ボーダーラインが見えてくるのではないかな、と思います。
1-1,もっと正確にボーダーラインを検証する
(ここの中身は非常に面倒くさいものとなっているので、大雑把な把握で構わないと思う人は次の見出しまで飛ばしてください)
まず、公民の授業で習う基本的な知識を振り返ります。
日本の選挙で比例区の議席を割り振る際に、使っている計算方法として『ドント式』というものがあります。
どういうものかというのはドント方式 – Wikipediaを見て欲しいのですが、大雑把に言うと、まずは得票数そのままで比較、そして1つ議席を確定させるごとに、政党の得票数を“÷その政党が確保した議席数+1”の式を適用した数字に修正して比較して議席を割り振っていく方式になります。
この方式を使っていることを前提に考えると、最後の議席を確保した政党にその最後の議席が割り振られた際の、『“÷その政党が確保した議席数+1”の式を適用した数字』を計算することにより、その選挙にて正確な1議席を確保するための最低基準が見えることになります。
以下に2001年以降の選挙でそれを計算した結果を示しておきます(使用した資料:参議院比例区 – Wikipediaなど)
- 2001年:約102万
- 2004年:約108万
- 2007年:約111万
- 2010年:約112万
- 2013年:約102万
この結果からしても100万弱強という参院選全国比例区1議席確保のための目標票数は概ね間違っていないように私は思います。
2,必要な得票率と、現在の日本を元気にする会支持率
先程の検証で出した、100万票弱強という数字、得票率にすると約2%になるようです。(比例区での改選議席数が48議席であることからも、2%近辺になることは妥当のように思う。100/48=2.0833333…なので死票がよほど出ないかぎりはそうなるのではないか。)
一方で、日本を元気にする会の支持率は、REAL POLITICS JAPANで調べたところ、最高で2015年5月の共同通信の世論調査での0.7%が最高で、そもそもそれ以外は良くて0.2%、殆どは0%という散々な結果になっています。
得票率2%という数字がどれだけ難しいものか、これでわかるのではないでしょうか?
ちなみに、2013年の参院選でノーマークから大量得票をしたが落選したということで、一部で話題になった三宅洋平氏の得票は約18万票、もし山田太郎議員の力のみで日本を元気にする会に議席を導くには、この6~7倍もの数字の得票を山田太郎議員が得ないといけなくなる。これまでの参院選、非拘束名簿式での個人名得票数の最高は、公明党の浜四津敏子氏の約182万票、2位は舛添要一氏の約159万票、3位、公明党の山本香苗氏約129万票約103万票であり(山本香苗氏は2001年と2007年の二回記録していて、そのうち2001年の記録を見逃し、そしてそちらのほうが得票数が多かったので修正しました。失礼しました)、それ以外の方は100万票を越えたことがないことからも、そのハードルはトンデモなく高いことがわかるだろう。
また、2010年の山田太郎議員の得票数は30,663票であり、同じ選挙を経て当選した人(山田太郎議員のような繰上げ当選を含む)の中では、最下位の田中茂参議院議員に次ぐ、下から2番めである。
結論とか雑記
このような散々な前提を見るに、よほどのテコ入れが、日本を元気にする会の比例議席確保には必要なのがわかると思います。
しかし、この『テコ入れ』が山田太郎議員の当選の事を考える場合、諸刃の剣になる恐れがあります。
例えば、現在噂として存在している乙武洋匡氏の出馬。もしこれが日本を元気にする会の比例区だった場合、知名度的にも山田太郎議員の個人得票を乙武洋匡氏が上回るでしょう。そうなった場合、日本を元気にする会が2議席を確保しないと山田太郎議員自身は当選できません。
もし乙武洋匡氏以外にもテコ入れとして知名度のある候補が増えていった場合、更に山田太郎議員の当選ハードルは上がってしまうのです。
このように、自分の党内の他の候補者と当落を争わないといけないというのが、比例区のジレンマといいますか、矛盾といいますか、候補者としてあまり望ましくない、つらい状況を作っているという話を、過去になんどか聞いたことがあります。
以上、指摘した内容で、山田太郎議員の再選にはとてもとても高いハードルが待っているというのがわかったと思います。しかしこのハードルをもし、乗り越えられたならば、とんでもないインパクトを社会に与えることが出来ると思います。
追記
この際分析はどうでも良いのですが、「100万弱」といったら99万とか98万で、「100万とちょっと」は「100万強」だと思うのですが、意図と記述が合っているのかが気になる
このような指摘を一年越しで発見し、確認したところこの指摘通りだったので、修正しました。ご指摘ありがとうございました。
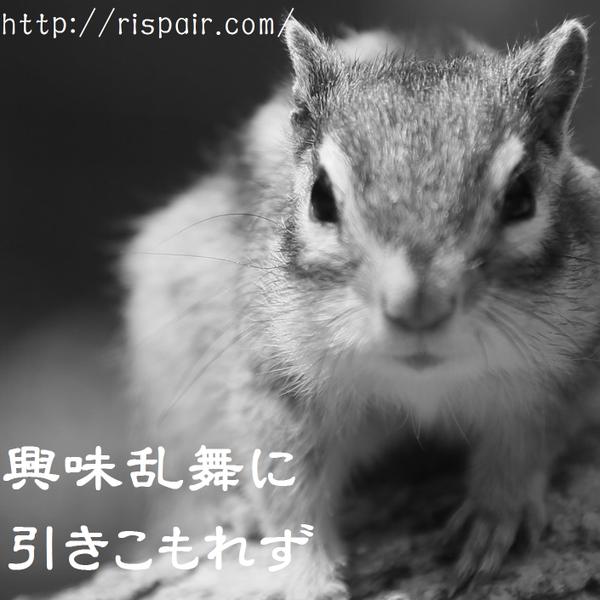
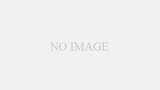
コメント